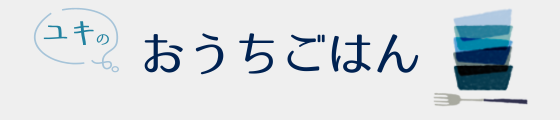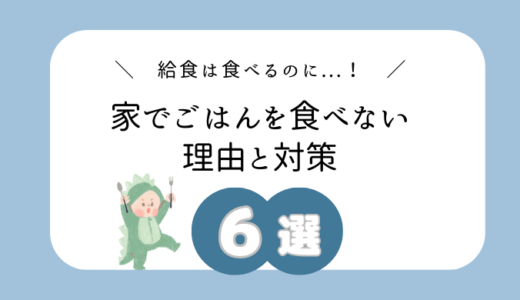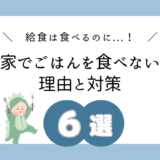この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
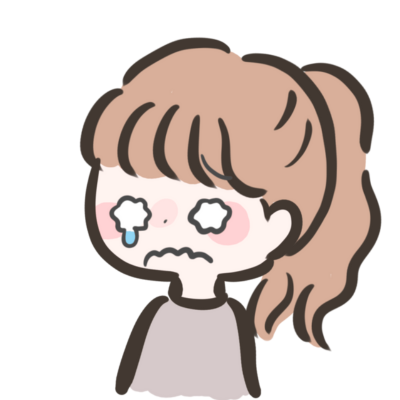
子どもの残したご飯もったいないから食べるけど
冷めててぐちゃぐちゃ…美味しくないし体重は増えるT_T

風邪がうつるのはイヤだから捨てちゃうけど、やっぱり心が痛む….
昨今、保育園や学校では「嫌いなものは無理して食べなくていい」という方針が浸透したように思います。
そんななか、家庭での子どもの食べ残しの対応で悩んでいるパパ・ママも多いのではないでしょうか?
私自身「もったいない」という感覚が強く、食べ物を捨てることにもストレスを感じていました。
でも、代わりに自分が食べると、自分の体重が増える・風邪がうつることもあるので
子どもの食べ残しは悩みのタネでした。
この記事では私の経験から
子どもが食べ残す→ 親が 食べるor 捨てる
を繰り返すストレス積み重ねの毎日から一歩抜け出した方法3つを紹介します。

この記事は主に幼児〜の内容となっています。
3兄弟子育て中の栄養士が、子どもの食べ残しに対する考え方を解説します。
- 残す原因を考える
- 食べ物について知る
- 食べ物や食べ物を作った人への感謝を示す
という3つの方法で
食事は楽しく!無理に食べさせることはしない
食べ残しを減らす(なくす)
を両立できるようになっていきます。
子どもの食べ残し、どうしてる?

- 残したものは親が責任を持って食べている
- 残したものは捨てている
- 「あとちょっと!」「がんばれ〜!」など励ましながら、最後まで食べさせる
などの意見が見られました。
わが家では、どうしても食べ残しが出てしまった場合、
- 食べ過ぎによる(私の)体重増加
- 風邪などうつるかもしれない
などのリスクを考えた上で、食べ残したものは捨てるor庭の野菜の栄養にしています。
でも、以下の3つを意識するようになってからは圧倒的に
子どもの食べ残しも、残されたときの自分のダメージも減少しました。
- 残す原因を考える
- 食べ物について知る
- 食べ物や食べ物を作った人への感謝を示す
どれも食べ残しを減らす・親のイライラの原因を取り除くのに大切なことなので、ぜひ最後までご覧ください!
子どもの食べ残し|食べる派

子どもの食べ残しを食べる派の意見として、
- 残すのは「もったいない」!
- 食べ物を粗末にしてはいけないことを子どもに伝えたいから
などがありました。

私も子どもの頃から、お米ひと粒も残さず食べるように教育されていました。
残して捨ててしまうとやはり、「もったいない」ですよね…。
子どもの食べ残し|捨てる派

子どもの食べ残しを食べない・捨てる派は、
- 食べ残しから感染症がうつるのを防止するためにも食べない!
- 全部食べていたら健康に良くないので、残ったら捨てる
などの意見が。

私自身、子どもの食べ残しを食べていた時期もありますが、
体重がどんどん増えていくことに焦りを感じキッパリ辞めました。
子どもの食べ残し|食べ物を「残す」以前に親ができること

食べ残したから「捨てる」「もったいないから食べる」より前に、親としてできることを考えてみました。
まず、食べ残しに対して悩んでいる自分の気持ちを整理すると、
・食べ残しを食べずに捨てることでストレスを感じる
・食べ残しを食べてもストレスを感じる
そんな自分の感情に気づきました。
この食べ残しによるストレスを解消するために至った結論は、できるだけ「食べ残しさせないこと!」

でも、無理に食べさせて食事の時間が苦痛にはなってほしくないし…

大丈夫!
子どもが自ら食べるようになってくれたらいいんです!
子どもの食べ残しは、親が「食べる」「食べない」以前に、
子どもに食べ物を大切にする気持ちを持ってほしい!と願っているパパ・ママが多いのではないでしょうか?
子どもの「食べ物を大切にする気持ち」を育てることで、
- 食べ残しは減らす(なくす)
- 食事は楽しく!無理に食べさせない
この2点を両立させられることに気がつきました。
子どもの食べ残し|子どもの発達状況も関係している!

「無理やり食べさせない」ことの前提として理解しておきたいポイントが1つあります。
それは、子ども(乳幼児)は特に、体も心も発達途中の段階だということ。
- 気分のムラで食べる量も変化しやすい
- 好き嫌いが固定化されていない
- 噛む力が未発達
- 子どもは大人よりも味覚が敏感
- 箸やスプーンに慣れていないため、途中で疲れてしまう
大人と同じようには食べられないのには、発達的な部分も大きいことを押さえておきましょう。
子どもの発達状況を無視して食べさせるのはNG。
子どもをよく観察して、食事の内容を考えることも大切です。

わが家の末っ子(3)は、乳歯が生えてくるのがゆっくりなようでお肉が苦手。
食べやすいよう柔らかく調理・小さめサイズにカットなど工夫しています。
子どもの食べ残しを減らす方法3選

残す原因を考える
 量が多い
量が多い
![]() 量を調整してから食べ始める
量を調整してから食べ始める
食べられたら少しずつ追加する「おかわり方式」がおすすめ。
大人であっても、食事の量が多すぎるとおなかが苦しいですよね。
子どもに食べさせたい気持ちから、つい盛りすぎてしまうことも。
「このくらいなら食べられる?」と子どもに確認してみるのも一つの方法です。
- 食べられなさそうな分は始めに調整
- お皿に盛られた料理は食べ切る
- 苦手なものも一口だけチャレンジしてみる
など家庭ごとでルールを決めて、自分で考え自分が食べられる量を学習することで
少し手をつけただけで大量に残すことがなくなり、物理的に食べ残しが減少。
全部食べられた!という自信も生まれるので自己肯定感を高めてくれます。
食欲がない
![]() 基本的な部分ですが、おなかがすいていないと食べ残しの原因になります。
基本的な部分ですが、おなかがすいていないと食べ残しの原因になります。
- おやつの量は適正か
- しっかり遊んでおなかは空いている状態か
- 体調は悪くないか
など、一度確認してみましょう。
食べている途中で疲れてしまう
![]() 食べている途中で集中力が切れてしまう場合、次のような項目を一度チェックしてみてください。
食べている途中で集中力が切れてしまう場合、次のような項目を一度チェックしてみてください。
- イスや箸・スプーンなどは子どもにあったものを使っているか
- 食事中に眠たくなってしまうようなら、しっかり睡眠をとれているか
イスは足裏が床(足台)につくもののほうが集中力が途切れにくいです。
また、サイズの合わない箸やスプーン類だと上手に使えず疲れてしまうことも。
簡単にできる工夫としては、
- 箸やスプーンのサイズを見直す
- 食べやすいように手づかみ食べできるメニューを取り入れる
- 箸やスプーンが使いやすいようなサイズにカットする
などがあります。
食事中に、うちの子疲れているかも?と思ったらぜひ試してみてください。
苦手な味や食感
![]() 子どもの味覚は大人よりも敏感。
子どもの味覚は大人よりも敏感。
苦味と酸味は本能的に嫌います。
今、無理に食べさせなくても成長とともに味覚も変わり
食べられるようになる場合も多いため、
どうしても苦手なものは無理にメニューに組み込まなくてもOKです。
食べ物について知る
食べ物に興味を持ってもらう
食べ物が登場する絵本などは、子どもでも楽しく知識を増やせる媒体の代表。
子どもが食べ物に興味をもつきっかけになります。
食べ物の生産・調理の過程を知ってもらう
子どもと一緒できる家庭菜園がおすすめ。
- 野菜を育てる
- 収穫する
- 料理する
- 盛り付けする
という一連の流れの中で、食べ物に対する興味が高まります。
始めは年齢や興味に合わせて、できるところからでOK。
栄養のこと・食べる理由を考えさせる
私たちの体は食べた物でできていること、なぜ食べないといけないのかを子どもに話すのも大切です。
というような具合で、実際に食卓に並んでいる食材を子どもに紹介してみると、
張り切って食べてくれることも。
食べ物や食べ物を作った人への感謝を示す
「いただきます」「ごちそうさまでした」は、日本特有の文化で
生きものの命をいただくこと・手間をかけてくれた人に対しての感謝の意味を表す言葉。
「いただきます」「ごちそうさま」の意味を子どもと一緒に考えることも重要ではないでしょうか。
少し重たい話題にはなりますが、
- 私たちが生きていくために、他の生きものの命をいただいていること
- 戦後の日本では食べ物が手に入らず、命を落とした人もいること
- 今も世界では、十分に食べられない子もいること
こんな内容も少しずつ子どもと話をしてみるのもいいかもしれません。
子どもたちにも、日本の文化「もったいない」「いただきます」など
人や食べ物に感謝する心・大切にする文化を伝えていきたいですね。

食の知識がなくても大切にできる部分なので、
個人的には「感謝する気持ち」は一番重要だと思ってます。
子どもの食べ残しを減らす方法|まとめ

子どもの食べ残しを減らす方法3つを紹介してきました。
- 残す原因を考える
- 食べ物について知る
- 食べ物や食べ物を作った人への感謝を示す
それでも食べ残しが出てしまうときは、家庭の方針で食べるor捨てるを決めていいと思います。
でも、「子どもだから残してもしょうがない」で終わらせずに、
- なぜ残ってしまったのか
- どのくらいの量なら食べられるか
を子どもにも一緒になって考えてもらうことが食べ残しを減らすことにつながると考えています。
子どもが小さいほど、理解できるまでには時間がかかります。
食に対する興味には個人差もありますが、準備段階だと思って根気強く話してみてください。
きっと、子どもなりに「食べ物を粗末にしちゃいけない」と理解していきます。
子どもも大人も一緒になって考えた上で、楽しく食事ができるといいですね。